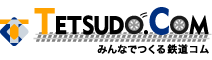JR発足当初は兄弟車が続々?
国鉄末期、各鉄道管理局では民営化に向けて各種のジョイフルトレインと呼ばれる車両が誕生していました。
その先駆けと言えるものは、1983年(昭和58)8月に東京南鉄道管理局で誕生したサロンエクスプレス東京であり、同年9月に大阪鉄道管理局のサロンカーなにわでした。
画像引用 wikipedia spaceaero2 - 自ら撮影, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6381118による
画像引用 wikipedia spaceaero2 - 自ら撮影, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7439622による
これらは、それまでのお座敷客車に変わる客車として誕生したわけで、若年層をターゲットとした車両として誕生したもので、その後各地で「ジョイフルトレイン」という名称で全国に広がることとなりました。
そこで、各管理局毎に既存の車両を改造した車両が多数誕生するのですが、そんな中国鉄末期には、前頭部の設計を流用したゆうとうピア和倉や サロンエクスプレスアルカディアと呼ばれる車両が国鉄末期に誕生することとなりました。
ご存じの通りこれらの車両は、北海道総局が開発した、アルファーコンチネンタルエクスプレスと同じ先頭形状であり、その設計図に関しては本社も全面的に応援したとされ、1986(昭和61)年に誕生しています。
同様に同様の設計で、アルカディアは、JR発足直前に誕生しているのはご存じのことと思います。
画像引用 wikipedia spaceaero2 - 自ら撮影, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5139169による
画像引用 wikipedia Goichiro Takeo - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15115941による
このように、国鉄という全国組織故に設計図を流用できた部分も大きく、会社は違えどアルファーコンチネンタルエクスプレスの基本設計をそのまま流用できた、そんな時代でした。
実際、発足直後は幹部クラスは元々本社にいたわけですので、○○君はJRのどこに居るなぁ。
それじゃちょっと、無理を聞いてもらおうか・・・的な発想になり得たわけで。
実際に、発足して数年はそうした空気感が漂っていたものでした。
やがて、各自独自の動きをするように
昭和63年4月、JR発足1周年では、各社が新しい制服を調達、会社の独自性が見られるようになりました。
この頃から、旧国鉄という意識は変わって行ったのでしょうね。
元々JR各社は同じ白色もしくは灰色のJRマークで申し合わせされていましたが、JR九州が当初からコーポレートカラーを採用していたこともあり、徐々に他社も自社のコーポレートカラーのマークを使用するようになりました。
JR西日本は、民営化後初めて投入された221系には正面にコーポレートカラーのJRマークが貼られ、JR東海も小さめのJRマークを経て、やがて小さなJRマークを車端に貼るようになり、いよいよ先祖返りしたようなイメージとなっていったのもこの頃でした。
それでも、ブルートレインは引き続き九州特急を中心に活躍し、新たに青函トンネルを通る夜行列車として北斗星が誕生するなど分割民営化しても国鉄時代のサービスは維持されると思われたのでした。
予想していたよりも順調な経営、やがて上場へ
当初噂された、将来的には再統合のためにJRマークの色は無彩色にしたという噂(その辺は、私もどこかで読んだ程度の記憶なので今後精査していく必要があります。)や実際に、当時の再建監理委員会も国鉄自身も分割民営化が成功するとは思っていなかったのです。
当時の再建監理委員会のシュミュレーションでは、国鉄はJR発足後も毎年値上げを繰り返し、5年後には収支が均衡するとしていました。
最も、歴史にIFはないですが、田中角栄が病に倒れることがなければ、国鉄改革もまた違った形で収束していたのではないでしょうか。